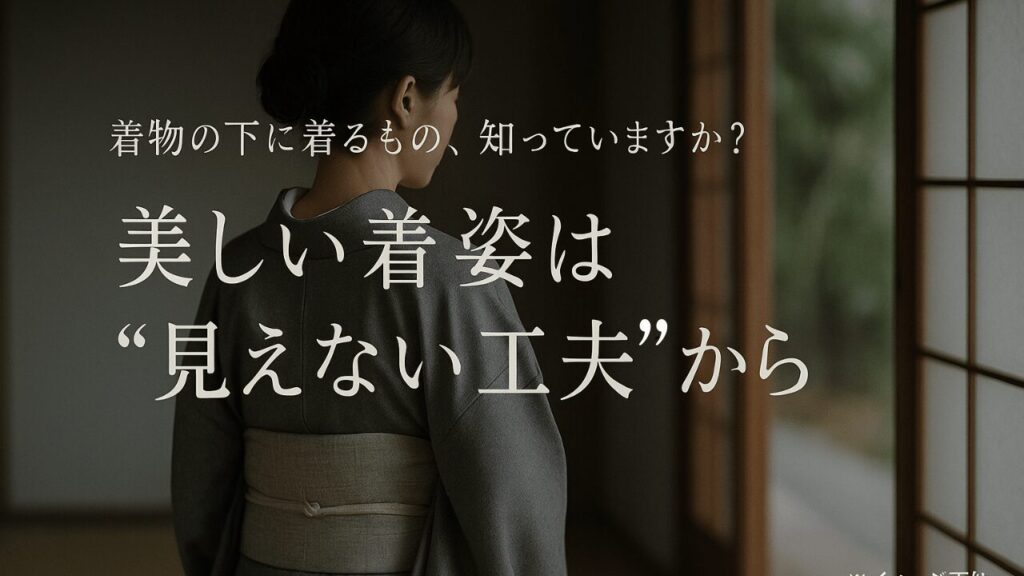
着物の下に着るものの種類と役割
着物を美しく着こなすためには、適切な下着選びが欠かせません。「着物の下に着るもの」と検索されている方は、初めて和装に挑戦する方や、より快適に着物を楽しみたいと考えている方が多いのではないでしょうか。実は着物の下に着るものには、肌襦袢や裾除け、長襦袢など様々な種類があり、それぞれが重要な役割を担っています。
女性が着物を着る際には、体型補正や汗対策、透け防止などの機能を持つ専用の下着が理想的ですが、キャミソールなどの洋服用インナーで代用することも可能です。また冬の着物では、ヒートテックなどの機能性インナーを活用した防寒対策も重要なポイントとなります。振袖のような特別な着物には、それに適した下着選びも必要です。
男性の場合も、着物の下に着るものは女性とは少し異なる特徴があります。最近では和装肌着としてユニクロなどの一般的なインナーを活用する方法も広がっており、着物をより身近に楽しめるようになっています。
この記事では、着物の下に着るものの名前や役割、季節やシーン別の選び方、そして代用アイテムまで、和装を美しく快適に楽しむための下着選びのポイントを詳しくご紹介します。初心者の方にもわかりやすく、着物愛好家の方にも参考になる情報をお届けしますので、ぜひ最後までお読みください。
-
着物の下に着る肌襦袢、裾除け、長襦袢などの基本的な種類と役割
-
季節や性別に応じた適切な下着の選び方と素材の特徴
-
洋服用インナー(キャミソールやヒートテック)での代用方法と注意点
-
着物姿を美しく見せるための下着選びのコツと着崩れ防止策
着物の下に着るもの 名前と基本構造

着物を美しく着こなすためには、適切な下着選びが欠かせません。着物の下に着るものには、それぞれ固有の名前と役割があります。まず基本となるのは「肌襦袢(はだじゅばん)」です。これは上半身に着用する下着で、直接肌に触れるため吸湿性に優れた素材で作られています。肌襦袢は前で合わせて紐で結ぶタイプが一般的ですが、最近ではノースリーブタイプやシャツタイプなど、現代的なデザインも増えてきました。
一方で下半身には「裾除け(すそよけ)」または「蹴出し(けだし)」と呼ばれるものを着用します。これは巻きスカートのような形状をしており、腰に巻いて紐で結びます。裾除けにもスカートタイプやパンツ型(ステテコ)など様々なバリエーションがあり、季節や好みに合わせて選ぶことができます。特にパンツ型は動きやすさが特徴ですが、帯を締める位置と干渉しないよう注意が必要です。
これらの上に着るのが「長襦袢(ながじゅばん)」です。長襦袢は肌着の中でも特別な位置づけにあり、着物の一部として見える唯一の下着です。衿元や袖口から覗く部分であるため、半衿を付けて装飾性を持たせることもあります。季節によって「単衣(ひとえ)」と「袷(あわせ)」の二種類があり、夏場は単衣、それ以外の季節は袷を選ぶのが一般的です。
近年では、肌襦袢と裾除けが一体になった「ワンピースタイプ」の肌着も人気を集めています。これはファスナーで留めるタイプや着物のように紐で結ぶタイプがあり、一枚で着用できるため着付けが格段に楽になります。ただし、衣紋(えもん)を抜きにくいという欠点もあるため、フォーマルな場では従来の分かれたタイプを選ぶ方が無難でしょう。
また女性の場合は、これらの下に「和装ブラジャー」を着用することが多いです。和装ブラは洋服用のブラジャーと異なり、胸を平らに整えるデザインになっています。ワイヤーが入っていないため長時間の着用でも苦しくなりにくく、着物の美しいシルエットを作るのに役立ちます。和装ブラは直接肌に付けますが、肌襦袢の代わりではなく、その下に着用するものです。
このように着物の下着は層構造になっており、それぞれが汗を吸収したり、着物の型崩れを防いだり、透けを防止したりと重要な役割を担っています。初めて着物を着る方は複雑に感じるかもしれませんが、これらの基本構造を理解することで、より美しく快適な着物姿を実現できるでしょう。
女性が着物の下に着るものの選び方
女性が着物を美しく着こなすためには、下着選びが非常に重要です。まず考慮すべきは「シーン」です。フォーマルな場面では、着物に合わせて正絹の長襦袢を選ぶことが望ましいでしょう。正絹は見た目が美しく高級感がありますが、水に弱いという特性があります。そのため、その下に着る肌襦袢は汗をよく吸う素材を選び、正絹の長襦袢を汗から守ることが大切です。
一方、普段着として着物を楽しむ場合は、お手入れのしやすさを重視して化繊の長襦袢がおすすめです。化繊は自宅での洗濯が可能なものが多く、気軽に着物を楽しみたい方に適しています。また肌襦袢や裾除けも、丈夫で長持ちする素材を選べば、頻繁に買い替える必要がなく経済的です。
季節による選び方も重要なポイントです。暑い季節には通気性の良い素材を選ぶことが快適な着物姿の秘訣です。長襦袢は単衣を選び、肌襦袢は木綿や麻など天然素材、あるいは吸水性や速乾性に優れた化学繊維の素材が適しています。特に夏場は汗をかきやすいため、汗取りの機能を重視した選択が必要です。
寒い季節の着物には、保温性を考慮した下着選びが必要ですが、着こみすぎには注意が必要です。長襦袢は袷を選び、肌襦袢は保温性のある化学繊維や、お手入れしやすい木綿や麻の素材がおすすめです。しかし、洋服のように重ね着をしすぎると動きにくくなったり、暑くなった場合に脱げないという問題が生じます。和装時の防寒対策は、肌着での重ね着よりも、羽織やコートを活用する方が賢明です。
素材選びも重要な要素です。天然素材である木綿や麻は、吸湿性や通気性に優れており、肌触りが良いため夏場に特に重宝します。また水に強いため家庭での洗濯も可能ですが、乾きに時間がかかるという特性があります。一方、化学繊維は速乾性や保温性など、特定の機能に優れた素材が多く、用途に応じて選ぶことができます。ただし、肌に合わない場合もあるため、自分の肌質に合った素材を選ぶことが大切です。
女性特有の悩みとして、生理中の着物着用があります。そんな時には、防水面が広いサニタリーショーツや、夜用など面積が広く吸水量の多いナプキンを用意するとよいでしょう。特に着物をレンタルする場合は、汚さないよう念入りな対策が必要です。経血量が多い日は、生理用オムツも選択肢の一つとなります。
このように女性が着物の下に着るものを選ぶ際は、シーン、季節、素材、そして個人の体質や状況に合わせた総合的な判断が必要です。適切な下着選びが、美しく快適な着物姿の基礎となるのです。
着物の下 キャミソールは代用できる?
着物の正統派な装いには専用の肌襦袢を使用するのが理想的ですが、キャミソールで代用することも可能です。特に着物初心者や、和装の機会が少ない方にとって、わざわざ専用の肌襦袢を購入するのは負担に感じるかもしれません。そんな時、普段使っているキャミソールが役立ちます。ただし、いくつかの条件を満たす必要があります。
キャミソールを肌襦袢の代わりに使う場合、最も重要なのは「衿元の開き」です。着物は背中や首元が大きく開くデザインのため、キャミソールの襟ぐりも十分に開いているものを選ぶ必要があります。具体的には、首の後ろの骨(第七頸椎)から5cm以上開いているものが適しています。もし襟ぐりが狭いと、着物の衿元からキャミソールが見えてしまい、着物姿の美しさを損ねてしまいます。
また、素材選びも重要なポイントです。キャミソールは直接肌に触れるものですから、汗をよく吸う素材を選ぶことが大切です。綿100%のものや、吸水速乾機能のある素材が適しています。特に夏場は汗をかきやすいため、通気性の良い素材を選ぶと快適に過ごせるでしょう。冬場であれば、保温性のある素材も選択肢に入りますが、厚すぎるものは避けた方が無難です。
色選びも見落としがちですが、実は非常に重要です。着物、特に薄手の生地の場合、下に着ているものの色が透けて見えることがあります。そのため、肌色や白など、目立たない色を選ぶことをおすすめします。特に黒や赤などの濃い色や派手な色は、着物から透けて見えやすいので避けるべきです。
キャミソールのデザインも考慮すべき点です。レースやフリルなど装飾が多いものは、着物の上から形が浮き出てしまうことがあります。また、パッド入りの胸元が強調されるタイプも、着物のシルエットを崩す原因となります。シンプルで平らなデザインのものを選ぶと、着物の美しいラインを保つことができます。
キャミソールだけでは不十分な場合もあります。例えば、正式な場での着物着用や、透けやすい薄手の着物を着る場合は、専用の肌襦袢を使用した方が安心です。また、汗をかきやすい方は、汗取りパッドが付いた専用の肌襦袢の方が機能的かもしれません。
ここで一つ注意点があります。キャミソールは上半身のみをカバーするものですので、下半身用の裾除けも別途必要になります。裾除けの代わりにはペチコートやスパッツなどで代用できますが、着物から見えない長さのものを選ぶことが大切です。
このように、キャミソールは条件を満たせば肌襦袢の代用として十分機能します。特に気軽に着物を楽しみたい方や、和装の機会が少ない方にとっては、既にあるものを活用できる経済的な選択肢と言えるでしょう。ただし、より本格的に着物を楽しむようになったら、専用の肌襦袢を揃えることも検討してみてください。
着物の下に着るもの 長襦袢の重要性

着物を美しく着こなすためには、適切な下着選びが欠かせませんが、その中でも特に重要な役割を担っているのが「長襦袢(ながじゅばん)」です。長襦袢は肌襦袢(はだじゅばん)の上に着用する和装肌着で、着物と肌着の間に位置する重要なアイテムとなります。まず長襦袢の最も基本的な役割は、大切な着物を汗や皮脂から守ることです。直接肌に触れる肌襦袢が第一の防御線となりますが、長襦袢はさらにその上から着物を保護します。特に首元や脇の下、帯を締める腰回りなど、汗をかきやすい部分の汚れから着物を守る役割は非常に重要です。
また、長襦袢は着物の着崩れを防止する効果も持っています。ツルツルとした滑りの良い素材で作られていることが多く、この特性によって着物との摩擦を軽減し、動きやすさを確保しながらも美しいシルエットを維持することができるのです。長時間の着用でも着崩れを最小限に抑えられるため、特に正式な場での着用には欠かせません。
さらに、長襦袢は季節に応じた体温調節の役割も担っています。夏場は「単衣(ひとえ)」と呼ばれる裏地のない薄手の長襦袢を選び、冬場は「袷(あわせ)」と呼ばれる裏地付きの長襦袢を選ぶことで、季節に適した着心地を実現できます。これは現代の洋服におけるレイヤリングの考え方と似ていますが、和装では古くからこうした知恵が活かされてきました。
長襦袢の魅力は機能性だけではありません。着物の衿元や袖口から覗く長襦袢は、コーディネートの一部としても重要です。特に衿元に縫い付ける「半衿(はんえり)」は、顔周りを彩る重要なアクセントとなります。フォーマルな場では白無地が基本ですが、カジュアルな場面では色や柄を楽しむこともできます。袖口から覗く長襦袢の色や柄も、さりげないおしゃれのポイントになります。
長襦袢の選び方にはいくつかのルールがあります。フォーマルな場面、例えば黒留袖や色留袖、紋付きの着物を着用する際には、白無地の長襦袢を選ぶのが基本です。一方、普段着の小紋や紬などカジュアルな着物の場合は、着物や帯とのコーディネートを考えながら、自由に色や柄を楽しむことができます。着物の格に合わせて長襦袢を選ぶことで、全体の調和が取れた美しい装いになります。
長襦袢の素材も重要な選択ポイントです。正絹(絹100%)の長襦袢は高級感があり、肌触りも滑らかで着心地が良いのが特徴です。ただし、お手入れには少し手間がかかります。一方、ポリエステルなどの化学繊維でできた長襦袢は、自宅で洗濯できるものも多く、お手入れが簡単という利点があります。最近では、絹の風合いを持ちながらも扱いやすい混紡素材の長襦袢も人気です。
このように長襦袢は、着物を美しく着こなすための土台となる重要なアイテムです。単なる下着ではなく、着物姿の美しさを左右する要素として、適切な選択と着用が求められます。初めて着物を着る方は、まずは基本的な白や淡いピンクなどの無地の長襦袢から始めると良いでしょう。着物の世界に慣れてきたら、少しずつ色や柄を取り入れて、自分らしい着物スタイルを楽しんでみてください。
振袖の下に着るものの特徴と注意点
振袖は若い女性の晴れ着として、特に成人式で着用される機会が多い華やかな着物です。そんな特別な日に美しく振袖を着こなすためには、下に着るものにも十分な注意を払う必要があります。振袖の下に着るものは、一般的な着物と基本的な構造は同じですが、いくつか特有の注意点があります。まず基本となるのは、直接肌に触れる「肌襦袢(はだじゅばん)」と「裾除け(すそよけ)」、そしてその上に着る「長襦袢(ながじゅばん)」です。これらは振袖を美しく着るための土台となる重要なアイテムです。
振袖の下に着る肌襦袢と裾除けには、上下が分かれたセパレートタイプと、一体型になったワンピースタイプ(着物スリップ)があります。初めて振袖を着る方には、着付けが比較的簡単なワンピースタイプがおすすめです。ただし、ワンピースタイプは「衣紋(えもん)」と呼ばれる首の後ろの開きを作りにくいという欠点もあります。衣紋をきれいに抜くことは振袖姿の美しさに直結するため、着付けの際には特に注意が必要です。
振袖の下に着るブラジャーは、通常の洋服用とは異なる「和装ブラ」が最適です。和装ブラは胸を平らに整える設計になっており、着物の美しいシルエットを作るのに役立ちます。ワイヤー入りのブラジャーは帯で締め付けられると痛みを感じることがあるため避けた方が無難です。和装ブラがない場合は、ノンワイヤーのスポーツブラやブラトップなどで代用することも可能です。ただし、バストアップ効果のあるパッド入りのものは避けるべきでしょう。
ショーツについても注意が必要です。振袖の下に着るショーツは、股上が深くウエストまであるタイプは避け、はき込み丈の浅いビキニタイプやローライズタイプを選ぶことをおすすめします。これは帯を締める位置と重なると着崩れの原因になるためです。また、レースやフリルなどの装飾が多いデザインも、振袖の上から形が浮き出てしまう可能性があるため避けた方が良いでしょう。
振袖の下に着るものを選ぶ際には、色にも注意が必要です。特に振袖が白や淡い色の場合、濃い色の下着が透けて見えてしまうことがあります。そのため、肌色や白など、目立たない色を選ぶことが大切です。特に黒や赤などの濃い色や派手な色は、振袖から透けて見えやすいので避けるべきです。
成人式は冬に行われることが多いため、防寒対策も重要なポイントです。しかし、振袖の下に着るものとして発熱インナーを選ぶ際には注意が必要です。多くの発熱インナーは襟ぐりが狭いため、振袖の衿元から見えてしまう可能性があります。選ぶなら首の後ろの骨から5cm以上開いているものがおすすめです。また、振袖は肌襦袢や長襦袢など複数の層を重ねるため、予想以上に暖かくなります。過度な防寒対策はかえって体調を崩す原因になることもあるため、バランスを考えることが大切です。
足元の防寒には、レギンスやスパッツが適しています。ただし、タイツは足元から見えると不格好になるため避けた方が良いでしょう。レギンスやスパッツも膝下までの長さのものを選び、振袖の裾から見えないようにすることが大切です。足先の寒さが気になる場合は、足袋ソックスを活用するのも一つの方法です。
最後に、振袖の下に貼るタイプのカイロは避けるべきです。振袖は一度着付けると簡単に脱ぐことができないため、熱くなっても取り外すことができません。これは低温やけどの危険性があります。寒さ対策としては、持ち歩きタイプのカイロやショールなどの着脱可能なアイテムを活用する方が安全です。
このように振袖の下に着るものは、見た目の美しさだけでなく、快適さや安全性も考慮して選ぶことが大切です。特別な日に後悔しないよう、事前にしっかりと準備しておきましょう。振袖レンタルを利用する場合は、下着類も含めてどこまでレンタルできるのか、事前に確認しておくと安心です。
着物の下に着るものの季節別選び方

着物の下に着るもの 冬の防寒対策
冬の着物姿を美しく保ちながら寒さを乗り切るためには、適切な下着選びが重要です。着物は洋服と違い、首元や袖口、足元など、隙間風が入りやすい構造になっています。しかし、正しい防寒対策を施せば、寒い季節でも快適に着物を楽しむことができるのです。まず基本となるのは、着物の下に着る肌襦袢(はだじゅばん)と裾除け(すそよけ)の素材選びです。冬場は保温性の高い素材を選ぶことで、体温の低下を防ぐことができます。特に綿や絹の混紡素材は、保温性と吸湿性を兼ね備えており、長時間の着用でも快適さを保つことができます。
また、寒さ対策として重要なのは「層構造」の考え方です。着物の下に複数の層を作ることで、空気の層ができ、それが断熱材の役割を果たします。例えば、肌襦袢の下に薄手の保温インナーを着用し、その上に長襦袢、そして着物という順番で着ることで、効果的な防寒対策になります。ただし、着こみすぎると動きにくくなったり、室内に入った時に暑くなりすぎたりする可能性があるため、適度な調整が必要です。
冬の着物で特に冷えを感じやすいのは、首元、手首、足首の「三つの首」と呼ばれる部分です。首元の防寒には、ショールやストールが効果的です。これらは室内でも自然に着用できるため、TPOに合わせて素材や色を選ぶとよいでしょう。手首の防寒には、長めの手袋やアームウォーマーが役立ちます。特にロンググローブは、袖口から入る冷気を防ぎながらも、着物の雰囲気を損なわない防寒アイテムとして人気があります。
足元の防寒も忘れてはなりません。冬用の足袋は、内側がフリース素材になっているものや、保温機能を持つ素材で作られたものがあります。また、足袋の下に足袋ソックスを重ねて履くこともできます。この場合、足袋のサイズを少し大きめに選ぶと良いでしょう。さらに、レギンスやスパッツなどを裾除けの下に履くことで、下半身の冷えを効果的に防ぐことができます。ただし、着物の裾から見えないよう、長さには注意が必要です。
冬の着物姿で注意したいのは、カイロの使用方法です。貼るタイプのカイロは、着物を着た後に取り外すことができないため、低温やけどの危険性があります。特に帯で締め付けられる部分にカイロを貼ると、熱がこもりやすくなります。防寒対策としては、持ち歩きタイプのカイロを使用するか、ポケット付きの和装小物を活用するのが安全です。
このように冬の着物の防寒対策は、下着選びから始まり、各部位に合わせた対策を組み合わせることが大切です。ただし、フォーマルな場では、和装の美しさを損なわないよう、目立たない方法で防寒することを心がけましょう。適切な防寒対策を施すことで、寒い季節でも着物本来の美しさを保ちながら、快適に過ごすことができるのです。
着物の下に着るもの ヒートテックの活用法

着物を寒い季節に着る際、多くの方が悩むのが防寒対策です。そんな時に頼りになるのが、ヒートテックなどの機能性インナーです。ヒートテックは着物の下に着るものとして非常に優れた特性を持っていますが、使い方には少しコツが必要です。まず知っておきたいのは、着物とヒートテックの相性は意外と良いということ。着物は何枚も重ね着するため、実は洋服よりも暖かいことが多いのです。特に胴体部分は肌襦袢、長襦袢、着物、帯と層が重なるため、ヒートテックの発熱機能が効果的に働きます。
ヒートテックを着物の下に着る際の最大の注意点は、衿元から見えないようにすることです。着物は衣紋(えもん)を抜いて着るため、首の後ろが大きく開きます。一般的なヒートテックは首元が詰まっているため、そのまま着用すると衿元からはみ出してしまいます。これを防ぐには、首元が大きく開いたUネックやVネックタイプを選ぶことが重要です。市販のヒートテックで適切なものが見つからない場合は、前後を逆に着るという裏技も。前側の開きが大きいデザインを後ろに持ってくることで、衣紋抜きに対応できます。
また、袖の長さにも注意が必要です。着物の袖口からヒートテックの袖が見えてしまうと、着物姿の美しさが損なわれます。そのため、七分袖以下の短めのものを選ぶと安心です。長袖のヒートテックしか持っていない場合は、肘あたりまで袖をまくっておくという方法もあります。屋外では袖を伸ばして防寒し、室内では袖をまくるという使い分けも可能です。
ヒートテックの色選びも重要なポイントです。万が一見えてしまった場合に目立たないよう、肌色や白など、着物と調和する色を選びましょう。特に薄い色の着物を着る場合は、濃い色のヒートテックが透けて見えることがあるため注意が必要です。また、着物の色に合わせた色を選ぶことで、万一見えても違和感を軽減することができます。
ヒートテックの暖かさレベルについても考慮すべきです。着物は複数の層を重ねるため、通常の洋服よりも暖かく感じることが多いです。そのため、極寒の日でも「極暖」タイプではなく、一般的なヒートテックや「薄手」タイプを選ぶのが無難です。ヒートテックは汗をかくとさらに発熱する特性があるため、着すぎると汗をかき、かえって寒く感じることもあります。特に室内と屋外の行き来が多い場合は、調整しやすい薄手のものがおすすめです。
下半身の防寒にはヒートテックのレギンスやスパッツが効果的です。これらは裾除けの下に履くことで、足元からの冷えを防ぎます。ただし、着物の裾から見えないよう、膝下までの長さのものを選ぶか、長いものは折り返して調整するとよいでしょう。また、レギンスの色も足袋との境目が目立たないよう、肌色に近いものを選ぶことがポイントです。
このようにヒートテックは着物の下に着るものとして非常に便利ですが、見えない工夫と適切な選択が重要です。着物の美しさを損なわず、かつ効果的に防寒するためには、衿元、袖丈、色、暖かさのレベルなど、細かな点に気を配ることが大切です。こうした工夫をすることで、寒い季節でも快適に着物を楽しむことができるでしょう。
和装肌着 ユニクロでの代用アイテム
和装を楽しみたいけれど、専用の肌着を揃えるのは予算的にも収納的にも負担…そんな悩みを抱える方は少なくありません。特に着物を頻繁に着ない方にとって、専用の和装肌着を購入するのはハードルが高いものです。そこで注目したいのが、日常でも使えるユニクロなどの一般的なインナーで和装肌着を代用する方法です。実は、適切に選べば洋服用のインナーでも十分に和装肌着の役割を果たすことができるのです。
まず、肌襦袢(はだじゅばん)の代用として活用できるのが、ユニクロのエアリズムやヒートテックのインナーです。季節に応じて、夏はエアリズム、冬はヒートテックを選ぶことで、快適な着心地を実現できます。特におすすめなのは、「エアリズムUネックT(半袖)」や「ヒートテックバレエネックT(8分袖)」などの首元が大きく開いたデザインのものです。これらは着物の衿元から見えにくく、和装の美しさを損なわないという利点があります。もし首元が詰まったインナーしか持っていない場合は、前後ろ逆に着るという裏技も。前側の開きが大きいデザインを後ろに持ってくることで、衣紋抜きに対応できるのです。
裾除け(すそよけ)の代用としては、ユニクロのステテコやレギンス、ペチコートなどが活用できます。夏場は「エアリズム素材の男性用ステテコ」が通気性に優れており、着物の裾さばきも良くなります。女性の場合は「エアリズムペチコート」も選択肢の一つです。冬場は「ヒートテックレギンス」が防寒対策として効果的です。レギンスを選ぶ際は、肌に近い色で、着物の裾から見えない長さのものを選ぶことがポイントです。
和装ブラジャーの代用としては、ユニクロの「ワイヤレスブラ(リラックス)」や「エアリズムブラタンクトップ」が適しています。これらは胸を平らに整える効果があり、着物のシルエットを美しく見せることができます。特にリラックスブラはシームレスでパッドも薄いため、着物に響きにくいという特徴があります。実際に着付け師から「和装ブラ?いいわねー!」と褒められたという口コミもあるほどです。
これらのアイテムを選ぶ際の共通のポイントは、「外から見えないこと」「着物の美しいシルエットを損なわないこと」「季節に合った素材であること」の3点です。例えば、派手な色や立体的なデザイン、レースやフリルが多いものは避け、シンプルで平らなデザインのものを選ぶことが大切です。また、バストアップ効果のある大きなパッドやワイヤー入りのブラジャーは、着物には不向きです。
さらに、生理中に着物を着る場合の対策も重要です。ユニクロの「AIRism 吸水サニタリーショーツ」などを活用し、長時間用のナプキンと併用することで安心して着物を楽しむことができます。特にレンタル着物の場合は、汚さないための対策が必須です。
このように、ユニクロなどの日常使いのインナーを工夫して選ぶことで、専用の和装肌着がなくても十分に着物を楽しむことができます。しかも、これらのアイテムは洋服の下にも着用できるため、コストパフォーマンスに優れています。着物を気軽に楽しみたい方、特に初心者の方は、まずは手持ちのインナーや身近なブランドのアイテムで代用してみることをおすすめします。着物の世界に慣れてきたら、少しずつ専用の和装肌着を揃えていくという方法も良いでしょう。着物文化を現代の生活に取り入れる柔軟な姿勢が、和装の楽しみを広げてくれるのです。
着物の下に着るもの 夏の快適な選択
夏の暑い季節に着物を着る際、下着選びは快適さを左右する重要なポイントです。汗ばむ季節だからこそ、適切な下着を選ぶことで、美しい着物姿を長時間保ちながら快適に過ごすことができます。夏の着物の下に着るものとして最も重要なのは、通気性と吸湿性に優れた素材の選択です。特に麻(リネン)は吸水性と発散性に優れており、夏の和装には理想的な素材と言えるでしょう。麻は肌に張り付きにくく、空気の通りが良いため、蒸し暑い日でも快適に過ごせます。ただし、麻100%の製品は素材がやや固いと感じる方もいるため、実際に触れてみてから選ぶことをおすすめします。
また、綿素材も夏の着物下着として人気があります。綿は吸水性に優れており、汗をしっかり吸い取ってくれるのが特徴です。特に楊柳(ようりゅう)と呼ばれる凸凹のある織り方をした綿素材は、肌への密着を防ぎ、通気性を高めてくれます。しかし、綿は吸った湿気を発散するのがやや苦手なので、二重になった厚手の綿素材は夏場には避けた方が無難です。夏の着物下着を選ぶ際は、薄手で軽やかな素材を選ぶことがポイントです。
夏の着物下着として注目したいのが、綿麻混紡の素材です。これは綿と麻を混ぜた素材で、麻の持つ優れた通気性と綿の柔らかな肌触りを兼ね備えています。麻特有の固さが苦手な方でも快適に着用できるうえ、価格も比較的リーズナブルなものが多いです。暑い日に長時間着物を着る予定がある場合は、このような混紡素材の下着を選ぶと良いでしょう。
夏の着物下着の種類としては、女性の場合、上半身には「肌襦袢(はだじゅばん)」、下半身には「裾除け(すそよけ)」を基本として着用します。最近では、これらが一体になった「ワンピースタイプ」の肌着も人気です。ワンピースタイプは着付けが簡単で、夏場の着崩れも防ぎやすいという利点があります。ただし、「衣紋(えもん)」と呼ばれる首の後ろの開きを作りにくいという欠点もあるため、フォーマルな場では従来の分かれたタイプを選ぶ方が無難でしょう。
夏の着物下着として忘れてはならないのが「長襦袢(ながじゅばん)」です。夏場は「単衣(ひとえ)」と呼ばれる裏地のない薄手の長襦袢を選びましょう。長襦袢は着物の一部として見える唯一の下着であり、衿元や袖口から覗く部分でもあるため、見た目の美しさも重要です。夏場は涼しげな色や柄を選ぶと、見た目にも涼やかな印象を与えることができます。
さらに、夏の着物下着選びで注目したいのが、最近の機能性素材です。速乾性や吸湿性に優れた化学繊維の下着も、夏の着物下着として人気を集めています。これらは汗をかいてもすぐに乾くため、長時間の着用でもべたつきにくいという特徴があります。特に汗をかきやすい方や、暑い屋外での行事に参加する予定がある方には、こうした機能性素材の下着がおすすめです。
夏の着物下着選びで忘れてはならないのが、色選びです。夏の着物や浴衣は薄手の生地が多く、下着の色が透けて見えることがあります。そのため、肌色や白など、目立たない色を選ぶことが大切です。特に黒や赤などの濃い色や派手な色は、着物から透けて見えやすいので避けるべきです。
このように夏の着物下着選びは、素材・デザイン・色など様々な要素を考慮する必要があります。適切な下着を選ぶことで、暑い季節でも快適に、そして美しく着物を楽しむことができるでしょう。夏の着物姿を最大限に引き立てるためにも、下着選びにはこだわりたいものです。
着物 下に着るもの 男性向けガイド

男性が着物を着る際の下着選びは、女性とは異なるポイントがあります。男性の着物姿を美しく見せるためにも、適切な下着選びは欠かせません。まず基本となるのは、直接肌に触れる「肌襦袢(はだじゅばん)」です。肌襦袢は上半身に着用する下着で、着物の着崩れを防止し、汗や皮脂から大切な着物を守る役割を果たします。男性用の肌襦袢は、女性用と比べてやや幅広で、肩幅に余裕があるデザインになっています。素材は吸湿性に優れた綿や麻が一般的ですが、最近では機能性素材を使った製品も増えています。特に汗をかきやすい方は、吸水速乾機能のある素材を選ぶと快適に過ごせるでしょう。
下半身には「裾除け(すそよけ)」または「ステテコ」を着用します。裾除けは巻きスカートのような形状で、腰に巻いて紐で結びます。一方、ステテコはパンツタイプの下着で、動きやすさが特徴です。特に夏場や活動的な場面では、ステテコの方が快適に過ごせることが多いでしょう。ただし、ステテコを選ぶ際は、帯を締める位置と干渉しないよう、股上が浅めのものを選ぶことがポイントです。また、着物から透けて見えないよう、肌色や白など落ち着いた色を選ぶことも大切です。
肌襦袢と裾除け(またはステテコ)の上に着るのが「長襦袢(ながじゅばん)」です。長襦袢は着物の一部として見える唯一の下着であり、衿元の美しさを左右する重要なアイテムです。男性の長襦袢は女性のものと比べてシンプルで、衿の幅が広いのが特徴です。季節によって「単衣(ひとえ)」と「袷(あわせ)」の二種類があり、夏場は単衣、それ以外の季節は袷を選ぶのが一般的です。フォーマルな場面では白色の長襦袢が基本ですが、カジュアルな場面では淡い色や柄物を楽しむこともできます。
近年、洋服のインナーで代用する男性も増えています。例えば、肌襦袢の代わりにUネックやVネックのTシャツ、裾除けの代わりにリラックスパンツやステテコを着用するという方法です。この場合、着物の衿元や袖口から見えないよう、首元が大きく開いたデザインや、袖丈が短めのものを選ぶことが重要です。また、着物から透けて見えないよう、派手な色や柄は避け、肌色や白など落ち着いた色を選びましょう。
冬場の着物では、防寒対策も重要です。ヒートテックなどの保温インナーを活用する場合も、着物の衿元から見えないよう、UネックやVネックなど首元が開いたデザインを選びましょう。また、厚手のインナーを重ね着すると動きにくくなるため、薄手で保温性の高いものを選ぶのがコツです。足元の防寒には、足袋の下に足袋ソックスを履くという方法もあります。この場合、足袋のサイズを少し大きめに選ぶと良いでしょう。
男性の着物姿で特に注意したいのが、下着のラインが着物の上から透けて見えることです。特に白や薄い色の着物を着る場合は、下着の色や柄が透けやすくなります。そのため、着物に合わせて下着の色を選ぶことが大切です。基本的には肌色や白など、目立たない色を選ぶのが無難です。また、装飾が多いデザインや立体的な縫い目のあるものは、着物の上からラインが浮き出てしまうことがあるため避けた方が良いでしょう。
男性の着物下着選びでもう一つ重要なのが、サイズ選びです。きつすぎると動きにくく、緩すぎると着崩れの原因になります。特に肌襦袢は肩幅に余裕があるものを、裾除けやステテコは腰回りがきつすぎないものを選びましょう。また、長襦袢は着物のサイズに合わせて選ぶことが大切です。着物と長襦袢のサイズが合っていないと、着崩れの原因になります。
このように男性の着物下着選びは、素材、デザイン、サイズなど様々な要素を考慮する必要があります。適切な下着を選ぶことで、快適に、そして美しく着物を楽しむことができるでしょう。初めて着物を着る方は、まずは基本的な和装下着から揃え、慣れてきたら自分の好みや体型に合わせてアレンジしていくのがおすすめです。
着物の下着選びで失敗しないコツ
着物の下着選びは、美しい着物姿を実現するための重要な第一歩です。適切な下着を選ぶことで、着崩れを防ぎ、長時間快適に過ごすことができます。下着選びで最も重要なポイントは、「着物のシルエットを美しく見せること」と「着心地の良さを確保すること」のバランスです。まず着物のシルエットを美しく見せるためには、ボディラインの凹凸をなだらかにする下着を選ぶことが大切です。着物は直線裁ちで作られているため、体のラインがそのまま出てしまうと、シワができたり着崩れの原因になったりします。特に女性の場合、バストやヒップのラインが強調されすぎないよう、適切な補正効果のある下着を選びましょう。
素材選びも重要なポイントです。着物の下着は直接肌に触れるものなので、肌触りの良さや吸湿性を重視することが大切です。天然素材である綿や麻は、吸湿性や通気性に優れており、長時間の着用でも快適に過ごせます。特に汗をかきやすい夏場は、これらの素材を選ぶと良いでしょう。一方、冬場は保温性を重視して、シルクや機能性素材を選ぶのがおすすめです。シルクは薄くても保温性が高く、着膨れしにくいという特徴があります。また、最近では「ヒートテック」などの機能性インナーを活用する方も増えています。これらを選ぶ際は、着物の衿元や袖口から見えないよう、デザインに注意することが大切です。
色選びも下着選びの重要なポイントです。着物、特に薄手の生地の場合、下に着ているものの色が透けて見えることがあります。そのため、肌色や白など、目立たない色を選ぶことをおすすめします。特に黒や赤などの濃い色や派手な色は、着物から透けて見えやすいので避けるべきです。また、柄物の下着も避けた方が無難です。柄が透けて見えると、着物の美しさを損ねてしまいます。
サイズ選びも失敗しないためのポイントです。きつすぎると動きにくく、緩すぎると着崩れの原因になります。特に長襦袢は着物のサイズに合わせて選ぶことが大切です。着物と長襦袢のサイズが合っていないと、着崩れの原因になります。また、肌襦袢や裾除けも、自分の体型に合ったサイズを選びましょう。特に女性の場合、バストサイズに合った和装ブラを選ぶことで、着物姿をより美しく見せることができます。
シーンに合わせた下着選びも大切です。フォーマルな場面では、正絹の長襦袢を選ぶことが望ましいでしょう。正絹は見た目が美しく高級感がありますが、水に弱いという特性があります。そのため、その下に着る肌襦袢は汗をよく吸う素材を選び、正絹の長襦袢を汗から守ることが大切です。一方、普段着として着物を楽しむ場合は、お手入れのしやすさを重視して化繊の長襦袢がおすすめです。化繊は自宅での洗濯が可能なものが多く、気軽に着物を楽しみたい方に適しています。
女性特有の悩みとして、生理中の着物着用があります。そんな時には、防水面が広いサニタリーショーツや、夜用など面積が広く吸水量の多いナプキンを用意するとよいでしょう。特に着物をレンタルする場合は、汚さないよう念入りな対策が必要です。経血量が多い日は、生理用オムツも選択肢の一つとなります。
また、着物の下着選びで失敗しないためには、試着することも大切です。特に初めて和装下着を購入する場合は、実際に着てみて着心地を確かめることをおすすめします。オンラインショップで購入する場合も、サイズ表をしっかり確認し、迷った場合は問い合わせてみるとよいでしょう。
最後に、着物の下着は洋服の下着と比べて種類が多く、初めての方は戸惑うかもしれません。しかし、基本的な構造を理解し、自分の体型やシーン、季節に合わせて選ぶことで、失敗を防ぐことができます。また、最近では従来の和装下着だけでなく、現代的なデザインや機能を取り入れた商品も増えています。自分に合った下着を見つけることで、着物をより快適に、美しく楽しむことができるでしょう。
着物の下に着るものの基本知識と選び方のポイント
- 肌襦袢は上半身用の下着で、直接肌に触れ汗を吸収する役割を持つ
- 裾除けは下半身用の下着で、巻きスカート状またはパンツ型(ステテコ)がある
- 長襦袢は肌襦袢の上に着る和装肌着で、着物の一部として衿元や袖口から見える
- 和装ブラジャーは胸を平らに整え、ワイヤーがなく長時間の着用でも苦しくない
- ワンピースタイプの肌着は肌襦袢と裾除けが一体化しており、着付けが簡単
- 季節に応じて長襦袢は単衣(夏用)と袷(それ以外の季節用)を使い分ける
- フォーマルな場では正絹の長襦袢、普段着には化繊の長襦袢が適している
- 夏は麻や楊柳綿など通気性の良い素材、冬は保温性のある素材を選ぶ
- キャミソールやTシャツなど洋服用インナーでも、衿元が開いたデザインなら代用可能
- ヒートテックを活用する際は、衿元から見えないよう首元が大きく開いたタイプを選ぶ
- 男性の和装下着は女性より幅広で肩幅に余裕があるデザインになっている
- 下着の色は肌色や白など目立たない色を選び、着物からの透けを防止する
- 生理中の着物着用には防水面が広いサニタリーショーツと長時間用ナプキンが有効
- 貼るタイプのカイロは低温やけどの危険があるため、持ち歩きタイプを使用する
- 着物の下着は層構造になっており、汗吸収・着崩れ防止・透け防止の役割を担う





